炭素循環農法で栽培された「ホッカイコガネ」を食べてみた。
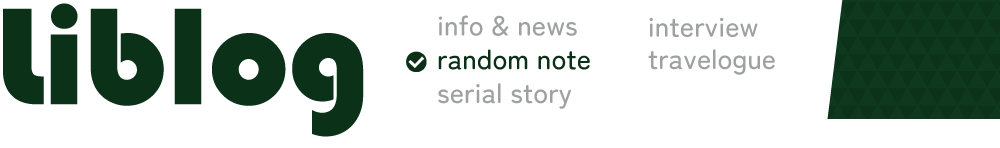

5月の中旬、植え付けを終えたばかりの我が里芋畑に、側を流れる稲作用の水路から大量の水が流入して、ものの見事に水没したことがあった。幸い、早期発見と迅速な対処が功を奏し、一時、絶望視されていた種芋たちは生還を果たし、現在、すくすくと成長を続けている。
ほっと一安心。
なんて思っていた矢先である。
今度はスズメガの幼虫(イモムシ)が結構な割合で繁殖していて、せっかく出てきた新葉を食い荒らしているのである。
おかげさまで、畑に行っては見つけたイモムシを除去する作業に追われる毎日。梅の収穫が終わる6月中旬以降は、少しのんびりできるだろうと思っていたが、一難去ってまた一難。農業はつくづく甘くない。
里芋栽培を始めて3年。こんな大発生は経験がなかったので、ネットでスズメガの幼虫の発生原因を調べてみたら、窒素過多の野菜につきやすいという情報に行き着いた。
― 窒素系の肥料を散布しすぎたのか。正直、心当たりがないわけでもない。
自然の自浄システムというのは、本当に良くできている。害虫の大発生もきっとそれによるものだろう。
自然の摂理に適った方法で農業を営んでいく。そういったことに正面から向き合っていかないといけない時期が来ているのかもしれない。
そんなことをおぼろげに考えていた先日のこと。
公私ともにお世話になっている友人Kさんの畑に、じゃがいも収穫の手伝いに行かせていただいた。この畑は、Kさんがじっくりと土づくりをしてきた畑である。




そのこだわりは、農薬や化学肥料を徹底的に排除することから始まる。長い時間をかけて土壌に微生物を根付かせ、その微生物の営みを利用して露地野菜を栽培するのだという。読者の皆さんも「炭素循環農法」という言葉をどこかで聞いたことがあるかもしれない。
Kさんはその農法の実践者の一人だ。
私自身、自然農法への憧れはあるが、慣行農法からの転換には、成功が保証されていない分、かなりの勇気がいる。
― 少しずつ始めてみるといいですよ。
そんなKさんの言葉を心に留めて、私は圃場を後にした。
その夜、収穫のお礼にいただいたじゃがいもをさっそく頂くことにした。
品種は「ホッカイコガネ」。
糖度がやや低く、ホクホクした食感と荷崩れしにくいのが特徴とのこと。男爵とメークインの良いとこどりといった趣のようである。1970年に北海道で加工用に品種改良してつくられたじゃがいもで、フライドポテトの黄金色から「ホッカイコガネ」と命名されたそうな。
フライドポテトはまあ、当然、作るとして、今回は、コロッケに挑戦。


なるほど。美味。
さっぱりした食感なので、正直、どんな料理にも合うタイプのじゃがいもといった印象。じゃがいも本来の味わいを楽しむというよりは、普段使いで活躍してくれそうな感じ。
とは言え、自分ひとりじゃ食の志向に偏りが出るので、他の人の感想も聞きたいところではある。
リブラ農園のご贔屓さまにおすそ分けでもしようかな。
そんなことを思案中……。

著者プロフィール
細谷豊明(リブラ農園・代表)/1975年北海道生まれ。イギリス留学後、出版社・編集会社での勤務を経て、食品宅配事業のWebサイト、カタログ制作のチーフエディターに就任。2019年、44歳のときに小田原市に移住し、未経験ながらも農業の道へ。元エディターの経験を生かして、新規就農者の視点から農業の現実をブログにて発信中。小田原市・認定新規就農者。

